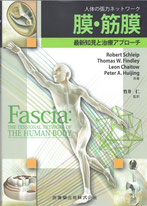この本の副題は「現代医学のミステリーに鍼灸の“サイエンス”が挑む!」というものでした。そして、著者のダニエル・キーオン氏は救急救命を専門とする医師でありながら、中医学と鍼治療の学位を取得され、著名な王居易医師に師事されたという経歴も持っていました。
つまり、この本は中医学および鍼治療を本格的に学ばれた医師が、現代医学の視点から経絡を分析したというものです。「これはすごい本だ」と思い、迷うことなく注文しました。
そして、腹に落ちたことは、『鍼治療とは、刺鍼ポイントのツボ(経穴)への刺激が、概念である氣の一部である「電氣」の知性に働きかけ、体表と内臓を結ぶ経路(経絡≒ファッシア)を通じて乱れた状態を元に戻す』というものでした。
また、ブログ「がんと自然治癒力13(まとめ)」で学んだことをかけ合わせれば『元に戻す』とは、『自然治癒力(ストレス適応を高め、栄養代謝を改善すること)によって、元に戻す』ということと考えています。
この本の概要を知るには、最後の“監訳者あとがき”をご紹介するのが良いと思います。
監訳者はNHK「統合診療医ドクターG」の医事指導も担当されている、津田篤太郎先生です。
津田篤太郎:京都大学医学部を卒業。医学博士。聖路加国際病院リウマチ膠原病センター副医長、北里大学東洋医学総合研究所客員研究員。
『本書は、英国の出版社Singing Dragonが2014年に出版した“The Spark in the Medicine:How the Science of Acupuncture Explains the Mysteries of Western Medicine”を翻訳したものである。著者のダニエル・キーオン(Daniel Keown)氏は、1998年にマンチェスター大学医学部を卒業した後、救急医療を専門とする医師として活躍するかたわら、2008年にキングストン大学統合医療カレッジで中医学を学び、2010年には北京の経絡医学研究センターで王居易医師に師事した。キーオン氏の東洋への関心は、80代の祖母から聞いた中国旅行の体験がもとになったという。原書を米国アマゾンのサイトで検索したところ、出版から数年を経ても(2018年4月現在)鍼灸・中医学分野の書籍で10位以内に入るベストセラーであり続けており、英米では東洋・西洋医学のギャップを埋めようとする著者の野心的な試みに、高い関心が寄せられていることがわかる。
本邦でも東洋・西洋医学を架橋する試みには江戸時代以来の長い歴史がある。劈頭(ヘキトウ[真っ先])となったのは杉田玄白(1733~1817)らの「解体新書」で知られる西洋の解剖学であり、日本人は西洋人の観察の緻密さに驚いた。しかし東洋医学の教える経絡のシステムを説明できるような構造物を見出すことができず、解剖学における位置づけは不明なままであった。幕末の名医、尾台榕堂(1799~1871)は著書「井観医言」のなかで、西洋医学・解剖学に関し「その論述する所は精細なりと雖も、亦た恐らくはかいせん無きを免れざらん」と評し、その理由として「死屍を解剖して、以って生人の機運を推す」からだと断じている。
生きた人間の「機運」、つまり機能と運動を科学的に解明するのは、意外と難しいことである。生きている、というのはうつろいやすい現象であり、科学が備えていなければならない客観性や再現性、整合性というものをすり抜けていく。この百年間ぐらいに、多くの研究者がさまざまな手法で経絡の正体に迫っていったが、どうやら経絡あるいは経絡で説明される現象が存在するようだ、という地点にとどまっていたように見える。例えば従来の電気生理学的手法では、定量性や客観性に優れるものの、「皮電点」「良導点」という名の通り、あくまで「点」のデータであり、経絡図のように生体の全体像に迫ることができない。また「ヘッド帯」「内臓体壁反射」など神経生理学的概念も、全体から迫るアプローチではあるものの、定量性・再現性にやや難があり、それですべての経絡現象が説明できるわけでもない。
しかし、その後も医療技術は進歩を続けた。私たちのわずか一世代前に開発されたCTやMRIといった画像診断法は、生きた人間を輪切りにして調べることができる革新的なモダリティーがある。そして、超音波診断(エコー)装置の精度の向上・小型化がここ10年ほどの間にすさまじい勢いで進んでいる。ついに、リアルタイムで生体の微細な構造までくっきりと見ることができる――現代の私たちは、だれもが古代の医聖、人体を透視することができたといわれる扁鵲(ヘンジャク)と同じ目で患者に接する時代を迎えたのである。

『扁鵲は、古代中国、とくに漢以前の中国における、伝説的な名医である。その行動、人格、診察、治療のありさまは「韓非子」や「史記」その他にさまざまな逸話を残す。』
画像出展:「ウィキペディア」
その最先端のエコーが、わが国の有訴者数ナンバーワンを競う腰痛・肩こりの治療で、大きな変化を引き起こしている。癒着を起こして動きの悪くなった筋肉の間に正確に針を挿入し、生理食塩水を注入する「エコーガイド下ハイドロリリース法」である。
この治療手技は速効性があり、症状の緩解率が高いことから、ここ数年の間に燎原の火のごとく普及が進んでおり、共訳者である須田万勢医師も、第一人者である隠岐島前病院の白石吉彦院長に学び、当院で実践している。

白石先生の記事を見つけました。『整形内科が診る腰痛、肩こり、五十肩』
医師が「扁鵲の目」を持った途端、筋肉の間の筋膜=ファッシアに注目するというのは偶然ではないだろう。従来の西洋医学で見逃され、たどり着けなかった暗黒大陸、それがファッシアであったというわけだ。奇しくも、本書の翻訳原稿を校了する数週間前にScientific Report誌で「ヒト組織における知られざる間質の構造と分析(Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues)」という論文が発表された。ニューヨーク大学などの研究チームは、共焦点レーザー顕微内視鏡という最先端の方法で胆管周囲の組織を調べたところ、コラーゲンなどの結合組織が網目状に規則正しく配列する構造を発見した。同様の組織は膀胱や皮膚、血管や気管の周囲、そして筋膜にも見出され、ネットのニュースなどで「人体における“最大の器官”が新たに発見された」と話題になった。
なぜこれまで発見されなかったのかというと、手術中に切り出された組織は、網目状の構造の中に存在する組織液が流出し、コラーゲンがただ単にしわくちゃに折り重なった状態で標本となり、検査されていたために、それが意味のある、研究に値する構造物であるとは誰も考えなかったのだ。ここでも、これまで見落とされてきた「生人の機運」が、最新の検査技術で初めて明らかにされつつあり、ミクロの扁鵲はやはり“筋膜”に出会うのである。
“筋膜=ファッシア”が長らく謎とされた経絡を解き明かす鍵概念だと断じた本書に、著者キーオン氏は「機械の閃光(The Spark in the Machine)」というタイトルを与えた。これはデカルト以来の「生命機械論」を下敷きにしているのだろう。しかし、鍼灸医学の経絡学説は「機械論」と対立する「生気論」の首魁(シュカイ[先駆け])ともいうべき存在であり、経絡学説が機械論、メカニズムで説明しつくすことができる、という著者の着想は大胆というよりほかない。しかも、目まぐるしく進歩を続ける医療技術は、著者の主張を日に日に補強するかの如くである。私たちは今まで見たこともないような形で経絡の正体が明らかにされるのを目撃するのであろうか、これからの展開に目が離せない。2018年4月16日 津田篤太郎』
目次は次の通りです。
プロローグ なぜ人体は再生しないのか?
PartⅠ 鍼のサイエンス 神が医者に話し忘れたこと
1.発生の創世記
2.単細胞の世界
3.有名にして無形
4.三重らせん
5.生命のスパーク
6.氣とは何か?
7.クローン羊と氣
8.完璧な工場
9.臓腑の氣
10.どのように氣が身体を折りたたむのか
11.トリッキー・ディッキーと小さな刺し傷
12.ヒトのフラクタル
13.レオナルドたちと完璧な人間
14.超高速の進化
15.ソニック・ヘッジホッグのパンチ
16.ツボ(経穴)とは何か?
17.氣の流れ
PartⅡ 中医学の発生学
18.陰陽に関する簡単な紹介
19.道(タオ)
20.羊膜外胚葉
21.身体の卵黄
22.血
23.精
24.発生学のサーファー
PartⅢ 命門と6本の経絡
三陰経
25.少陰経
26.太陰経
27.厥陰系
三陽経
28.太陽経
29.陽明経
30.少陽経
エピローグ
付録
監訳者あとがき
参考文献
索引
ブログは4つに分けてアップしたいと思います。
今回の題名は“経絡と電氣”です。これはPartⅠの「鍼のサイエンス」が対象です。他は、PartⅢの少陰経から“心と腎”、同じくPartⅢの厥陰経から“肝と機能性子宮出血”、そして付録3から“関連痛とは”という題名になります。
“経絡と電氣” という題名を付けたのは、「がんと自然治癒力13(まとめ)」の最後、ブルース・リプトン先生の著書である “思考のすごい力” に書かれていた一文を意識してのことです。それは今まで一度も考えてみたこともない、とても印象的な視点で鍼灸・経絡を語られていました。
『東洋医学では、身体はエネルギーの経路(経絡)が複雑に列をなしたものと定義される。中国の鍼灸療法で用いられる人体の経絡図には、電気配線図にも似たエネルギーのネットワークが描かれている。中国医学の医師は、鍼などを用いて患者のエネルギー回路をテストするわけだが、これはまさに電気技師がプリント基板を「トラブルシュート」して電気的な「病変」を発見しようとするのと同じやり方だ。』
一方、今回の「閃く経絡」の中にも電氣(一般的な電気と区別するときに「電氣」という漢字が用いられています)について触れている部分は多く、経絡を電氣という視点から考えまとめることは、ブルース・リプトン先生によって投げかけられた生体内システムの謎に近づけるのではないかと思いました。これが“経絡と電氣”というタイトルにした理由です。
“経絡と電氣”に紐づくキーワードは6つです。ブログはこの6つについて書いています。
1.経絡
2.ファッシア
3.コラーゲン
4.氣
5.バイオフォトン
6.ツボ(経穴)
1.経絡
専門学校で学んだ『東洋医学概論(東洋療法学校協会編)』の「3.臓腑経絡論」を見ると、経絡について次のような説明をしています。
『経絡について考える場合には、経絡現象と、それを基にして形成されてきた経絡説と区別して認識する所から出発しなければならない。
経絡現象は、特定の身体部位を指先で押したり、鋭利な石片(“砭石(ヘンセキ)”と呼ばれている)を刺したり、あるいは、刺して皮膚を傷つけて出血させたりする治療行為をする際に、おそらく発現していたのであろうと考えられる。日本で“針の響き現象”といわれている、針を刺したときに発生する特殊な感覚の伝達現象もその一つである。また、一定の部位に針を刺したときに、その部位の苦痛が緩解されるばかりでなく、遠隔部位にまで変化が波及することも含まれよう。
経絡説は、そのような経絡現象を基にして、その性質や現象の発現のルールを極めようとして考え出されてきたものである。したがって、経絡説は、それが形成されてきた時代の思考法や社会制度などに影響されざるをえない。』
続いて、「1)経絡概説」にて“経絡説の成立ち”、“経絡の構成”、“経絡の機能”、“十二経脈について”、“奇経八脈”、“そのほかの経絡系”の6つの説明が加えられていますが、ここでは冒頭部分と“経絡説の成立ち”のみご紹介させて頂きます。
『経絡とは、気血の運行する通路のことであり、人体を縦方向に走る経脈と、経脈から分支して、身体各部に広く分布する絡脈を総称するものである。
経絡の考え方は、古代中国人が、長い臨床観察を通じて得た一つの思考体系であり、蔵象とならんで東洋医学の根幹をなすものである。特に鍼灸医学にあっては、診断と治療に深く係わっており、きわめて重要である。』
注)蔵象に関する説明:『東洋医学では、内臓について、これを単なる体の構成部分ではなく、経脈とならぶ人体の生理的、病理的現象や、精神活動の中心となるものとしてとらえる。これを「蔵象」とよぶ。「蔵」とは、体内にしまわれている内臓をさし、「象」は、外に現れている生理的、病理的な現象をさしている。』
“経絡説の成立ち”:『春秋時代(紀元前770年から、「晋」が三国に分裂した紀元前5世紀までのおよそ320年の期間)以前には、気の概念は広まっておらず、したがって、経脈(あるいは経絡)という考え方は存在しなかった。当時には、血脈という語があり、血の通路としてのすじ(今日でいう血管)を認識していたにすぎなかった(「史記」:扁鵲伝)。
戦国時代(「晋」が分裂した紀元前5世紀から「秦」が中国を統一する紀元前221年までの期間)から前漢時代(紀元前206年-紀元後8年)にかけては、体表部を三陰三陽に分けて走行する経脈を認識するに至った。これは後に完成する経絡説の原型となるものであり、気の通路を想定していたものといえる。しかし、この時代の経脈は、内に臓腑と結びつくという認識には至らなかった(「史記」:倉公伝、「馬王堆医経」』)。
前漢から後漢(25年-220年)にかけては、陰陽・五行説が、医学に十分浸透した時期であり、三陰三陽の十二経脈が、天の十二月や地の十二水との相応において認識され、また、各経脈が、体内の五臓(六臓)六腑と関連づけられるようになり、経絡系統なるものが確立した。この時代に完成した経絡説が、約二千年を経た今日まで受け継がれてきたのである(「素問」:離合真邪論篇、「霊枢」:経水篇、五乱篇)。
下は経絡の流れである「琉注」の図です(画像出展:「経穴マップ」)。手と足の三陰経と三陽経の計十二の経脈と、奇経に分類されている体前面正中の任脈、後面正中の督脈の二つを加えた十四の経脈が出ています。このうち手足の三陰経、三陽経の琉注は、体表だけなく体内の臓腑につながるものであることが示されています。
一方、自律神経反射の一つ「体性-内臓反射」という反射があります。ネット上の『痛みと鎮痛の基礎知識』に書かれている説明は次のようなものです。
『体性-内臓反射(体性*交感神経反射):皮膚に侵害性刺激を加えると交感神経系の機能が亢進し、交感神経が緊張し、血圧の上昇、心拍数や呼吸数の増加などを引き起こす。』
この「体性-内臓反射」も体表と内臓を結びつけるルートといえますが、経絡の多様性と比較するとその差は大きく、経絡とは一線を画すあくまで自律神経反射の域を超えるものではないと思います。
その自律神経反射に比べると、ファッシアの「体表と内臓のつながり」、「固定的な点-線を越えた面という多様性のあるひろがり」の二つの特徴は経絡を連想させるものであり、「経絡≒ファッシア」について追及することは、ヒトのからだの理解を深め、施術の質を高めるうえで極めて価値あるものと思います。(ただし、生まれと育ちが異なる「東洋医学の経絡」と「西洋医学のファッシア」が≒の域を超え、=で結ばれることはないと考えます)
2.ファッシア
ファッシアという言葉は最近見かけるようになりましたが、ファッシアについては、テレビでもご活躍されている、首都大学東京の竹井仁先生が監訳された『人体の張力ネットワーク 膜・筋膜 最新知見と治療アプローチ』にその定義が出ていますので、そちらの内容をご紹介させて頂きます。
『Fascia(膜・筋膜)は、身体全体にわたる張力ネットワークを形成し、すべての器官、あらゆる筋・神経・内臓などを覆って連結しています。筋膜に関する研究はここ30~40年ほどで大きく発展しました。それまでは、皮膚、浅筋膜、深筋膜などをいかにきれいに取り去り、筋外膜に覆われた筋を露出させるかに力が注がれてきました。また、どの筋が骨を介してどのような作用をするかに関しての研究が主流でした。
しかし、生体においては、筋群の最大限の力が骨格への腱を経て直接的に伝達することは少なく、筋群の作用は、むしろ筋膜シート上へと、収縮力あるいは張力の大部分を伝えることがわかってきました。また、これらのシートは、共同筋ならびに拮抗筋にこれらの力を伝達し、それぞれの関節だけでなく、離れたいくつかの関節にも影響をおよぼすことも明らかになってきたのです。さらに、筋膜の剛性と弾性が、人体の多くの動的運動において重要な役割を果たすことも示されてきました。これらの事実は、新しい画像診断や研究手法の開発によって飛躍的に明らかになってきました。
2007年10月にHarvard Medical Schoolで開催された第1回国際筋膜研究学術大会(The 1st International Fascia Research Congress)において、「Fascia」は、「固有の膜ともよばれている高密度平面組織シート(中隔、関節包、腱膜、臓器包、支帯)だけでなく、靭帯と腱の形でのこのネットワークの局所高密度化したものを含む。そのうえ、それは浅筋膜または筋内の最奥の筋内膜のようなより柔らかい膠原線維性結合組織を含む」と定義されました。』
この本は「科学的基盤」「臨床応用」「研究の方向性」の3部から構成されています。『閃く経絡』の内容に関係するような箇所も多数あり、補足するようなかたちでお伝えできると良いのですが、理解がまったく追いついていないため、ブログの最後にこの本の大項目、中項目の目次だけをご紹介させていただきます。
以下の二つは、『閃く経絡』からの抜粋です。
『ファッシアは臓器の輪郭をはっきりと示し、内部に閉じ込める。そして、生物学的な物質がファッシアの向こう側へ通過することは難しいが、ファッシアに沿って通過することは比較的簡単であることはわかっている。これは、体液、ホルモン、血液、空気、そして電気にもあてはまる。外科医はこの事実を理解して毎日利用していることから、このことは正しいとわかる。癌の悪性度は、このルールを曲げてしまう度合いによって定義される。つまり、健康であれば、ファッシアを通り抜ける物は存在しない。』P57
『各臓器はファッシアの中に入っている。しかし、それらもまた別の臓器とつながっている。いつ成長を止めるかをどのように知るのだろう? なぜ互いに侵入したり、血液を横取りしたりしないのだろう? 臓器はともに成長するだけでなく、ともに生きるためにもコミュニケーションをとらなければならない。すべての折りたたみは基本的には単純である。しかし、「何」が折り重なるように身体に指示しているのだろうか?
臓器が他の細胞に影響を及ぼす物質を分泌することはわかっている。我々の身体は、常に、他の細胞や臓器にメッセージを伝える大量のホルモンでごった返している。アドレナリンやインスリンといったホルモンを産生する副腎や膵臓といった腺組織だけでなく、すべての免疫細胞は常に神経伝達物質を産生し、心臓の細胞は利尿ホルモン、腸はセロトニンなど、その他もろもろ作っている。これらのホルモンは血液によって伝達され、臓器が身体の残りの部分といっせいにコミュニケーションをとることができる。』P58
“臓器どうしのコミュニケーション”と聞いて思い出すのは、NHKスペシャル “人体 神秘の巨大ネットワーク” という番組です。このイラストは書籍版の第1集に出ていたものです。
『氣には通路が必要である。身体の中にファッシア以外にふさわしい通路があるだろうか? ファッシアの層の間に完全に独立した通路を維持しながら、すべての物をつなげて包んでいく。ファッシアの通路は解剖学者によって説明されているが、彼らが説明したのはファッシアではなく、ファッシアが包んでいる組織である。』P105
『鍼治療を受けた患者が特に手足でよく訴える感覚の1つが、電気的な感覚である。いくつかのツボでは、特に手足末端でうずく感覚や、電気が伝播する感覚が引き起こされる。研究によると、鍼灸のツボは周囲の皮膚よりも電気伝導性に優れている。そして、鍼灸の経絡は、周囲の組織よりも電気伝導性に優れている。経絡もツボもファッシアに存在する。王居易医師との議論や私自身の診療経験から、私はツボがファッシアに存在することを完全に確信している。コラーゲンがファッシアの主成分であり、そしてコラーゲンには変わった導電特性があり、電気も生成する。最も重要なのは、ファッシア面の間にある液体は電気を非常によく伝導することだ。この液体にはいかなる物理的な障害もない……健康であればだが。』P106
『コンピュータが電気によって動いている現実を、我々は平気で受け入れている。コンピュータが生きているか死んでいるかの違いは、ソフトウェアか電気のどちらかが原因になることが多い。全く同じように、死(心臓死でも脳死でも)は、医学的に身体の「電気的特性」によって定義される。
-中略-
コンピュータもヒトもエネルギーの不具合を抱えることがあるにもかかわらず、問題なのは、西洋医学がほぼ完全にこの現実を無視していることだ。身体には、身体の各部を結ぶ目に見えないエネルギーの網が張り巡らされている。それは、成長し、機能するためになくてはならない。何か故障が起きたとき、神経系が我々に意識に上ると気づくことができるが、それは器質的な損傷に至る前のことかもしれない。痛みはメッセンジャーであり、それ自体が問題なのではない。医師は最も敏感な器具、つまり自分自身を使う代わりに、身体の器質的な損傷を測定する機械にますます頼るようになってきている。もし、あなたの身体がコンピュータだとしたら、風邪で医師に見てもらっても測定できないため、意味がないだろう。ウィルスが物理的に回路を壊し始めるまで待たなければならない。
しかし、この微妙なエネルギー障害こそが重要である。理由があるから症状が出る。それらは警告のサインなのだ! 痛みは危険信号であり、身体があなたの行動を変えさせようとしている。痛みをなくすことで問題解決になることはめったにない。それはただメッセンジャーを消滅させているだけである。
エネルギー障害がすべての病気の中心にある。そして、それらはすべての病気の前兆だと言える。あらゆる病気の中で明らかに最も「器質的」なものに属する外傷でさえ、実際のところ単に体内での過剰なエネルギーの消耗が問題なのである。』P106
3.コラーゲン
まずは本書の中に出ているコラーゲンを説明した箇所をいくつかご紹介します。
『ファッシアの主な成分は、コラーゲンである。コラーゲンは身体の至る所にあり、ファッシアだけでなく、腱、靭帯、関節の軟骨などを形成している。また、動脈壁にも存在するほか、骨に伸長強度を与え、臓器内の結合組織も形作っている。さらに眼のレンズを形成して見ることを可能にしたり、瘢痕組織を作って傷を治したりもしている。コラーゲンは身体のタンパク質の約3分の1を占めている。』P23
『コラーゲンの構造は原子レベルで作られ、莫大な強さを与えられる。それは、同じ重さで言えば、鋼の強さにも匹敵する!コラーゲンは骨、動脈、筋、腱、筋膜のベースとなる素材であるため、この強靭さは生命に関わるほど重要になる。』P25
『西洋医学では完全に無視されているが、電気的特性を持っている。コラーゲンには圧電性の特性があるのだ。それは、物が変形するときにわずかな電流を発生させる。同じ原理で、小さな水晶の結晶を変形させることによって、ライターの火花は魔法のように発生する。つまり、我々の身体のありとあらゆる部分が動くたびに、いつも小さな電流が生じているのである。』p26
『骨におけるコラーゲンの役割は、強度を与えることよりも驚くべきことがある。コラーゲンは半結晶物質であり、この結晶の特性の1つが圧電性を持つということだ。ある論文の著者が言うように、骨にも圧電性がある。その論文にはこう書かれている。「骨を非コラーゲン化すると、ピエゾ効果(圧電効果)が失われることがわかった。つまり、骨の圧電気の主要な成因はコラーゲンである」』p27
『電気を発生させるという特性を持つのは、骨ではなくコラーゲンで、ファッシア内の他のコラーゲンも同じ種類である。ファッシアのコラーゲンは機械的ストレスの線に沿って存在し、伸ばされたり動いたりする度に小さな電気を発生させる。この電気を西洋医学の医師は完全に無視した。どの医師に尋ねてもおそらくぽかんとするだけだろう。それにしても、身体の組織を連結させ、全身を包み結合しているファッシアが実際のところ、相互接続している、生きた電気の網であることには全く驚かされる。これは、古代中国における経絡や氣の記述と非常によく似ている。』p29
『コラーゲンは電気を生むだけでなく、伝導の特性も持つ。つまり、半導体なのだ。言い換えるなら、完全に絶縁体・伝導体のようにふるまうわけではない。コンピュータに「知性」を与えるものと同じ特性と言える。』
『このコラーゲンの電気的性質によって、身体のすべてのものが電気的になるということは実に面白い。すべての細胞表面には肺と同じくらい生命に不可欠となるポンプが存在する。このポンプは、2つのカリウムイオンを取り込むことと引き換えに、3つのナトリウムイオンを放出する。これによって細胞内は負の電荷を帯びる。結果として、細胞全体にわずかな電荷が生じる。この帯電なしでは、細胞は機能しない。ポンプが数分間止まっただけでこの電荷はなくなり、細胞は膨らみ、死んでしまう!電気は生命に必要不可欠である。』
『体内での電気の効果は、細胞を生存させる仕事だけではない。身体の神経は情報伝達に、筋肉は収縮する力に、脳は考えるために使用している。心臓のリズムは電気的なペースメーカーによって生じ、眼さえも光を調節するのに電気を使用している。』p30
『ベッカー(Robert O. Becker)がいうように、我々は本当に「電気の身体」であり、常に光速で身体中に広がる目に見えない静かなエネルギーを発散・吸収している。』p31
『あらゆる生理学的プロセス、すべての動き、すべての考えが、実体として2つの要素 ―物理的な実体とエネルギー的な実体― を持っているように思える。心臓が鼓動すれば、その物理的な動きを手で感じたり、超音波で確認したりできる。しかし、電気的な実体は、心電図(ECG)を用いれば、よりはっきりと見ることができる。このエネルギー的な実体が物理的な実体よりもリアルであり、より簡単に測定できることから、西洋医学ではこちらの検査を多用している。』P31
『この電気的世界の中心にコラーゲンがあり、生体にあまねく存在し、生体のすべてを結合させている。コラーゲンは結合組織の主要な構成成分であり、その強さにより人体が支えられていることは西洋医学にも認められている。コラーゲンは身体において電気的半導体としても、またピエゾ電気の発電装置としても傑出した存在であり、その重要性は機械的に強いというコラーゲンの特徴を上回るかもしれない。いや、むしろ、コラーゲンは、あるときは半導体として働き、またあるときはピエゾ電気を発電する生体らせん物質であり、体内の電気を保持し、発電し、流れる方向を導くことさえできる「スーパー伝導物質」とみなされるべきなのだ。電気の力は、身体を編んでいる組織の中に保持されている。この科学は中医学や氣のような響きを帯び始めてくる。』P31
4.氣
氣に関しても、ポイントと思われる個所を列挙します。
なお、経絡≒ファッシアを考えるときに、コラーゲンの電気特性と共にこの「氣」に関する内容が本書の中核ではないかと思っています。
『語源学の観点から、氣は空気と同じであると思われる……そして、古代の人がなぜ人体のような固体物質に対して氣のような言葉を用いたのかという疑問が生まれてくる。もちろん人体の中に空気は存在する。肺の中には空気が存在し、血液や体液中には空気が溶けている。この空気は主に酸素と二酸化炭素であり、微量ではあるが、窒素や他の気体も含まれている。二酸化炭素と酸素から成る空気は、我々の代謝の基礎中の基礎と言える。事実、これら2つの気体のみが、いかなる時代においても身体の「代謝」を解明する科学的研究に用いられている。』
『楊俊敏博士は ”気功の理解(Understanding Qigong)” と題された一連のDVDで、非常に簡潔にこの文字の説明をしている。古代の中国人は、医学において最も単純な方程式の1つをただ描いたにすぎないのだ。
食物+空気=エネルギー
グルコース+酸素=水+二酸化炭素+エネルギー
C6H12O6+6O2=6H2O+6CO2+エネルギー
氣という文字の特徴は、米と空気が混ざることでエネルギーが作られることを表している……これが生物学的な意味での氣である!』P34
『氣は「代謝」? 氣は「空気」? 氣は「空間」? 一体どれが正しいのだろうか? 答えはすべて正解であり、かつそれ以上の存在でもある。代謝エネルギーは、ある意味では、空気によって定義される。生物に空気の供給を止めると、氣も代謝もなくなってしまう。しかし、氣は物質とするにはあまりにも幅が広い。氣はより観念的な存在である。そのため、西洋の科学が氣をどう位置づけるかに苦労する1つの理由になっている。氣は科学よりも哲学、発想や抽象概念に近い存在である。とはいえ、抽象概念は科学的論拠の核心部分を保っている。』
『氣は身体を組織する力である。それは、知性を持った代謝、もしくは、よりよい表現を求めるのならば「生命力」と言える。氣はあなたが行うあらゆる動き、そして、肺の呼吸、ミトコンドリアの呼吸、あらゆる呼吸に存在する。氣がどのように身体を組織しているかを理解するために、我々はミトコンドリアから、細胞、組織、臓器へと考えてきた。我々は、40億年にもわたる細胞の協調に関して早送りして見てきた。それでも、氣がどう作用するかについて少ししかわからない。』P104
『モルフォゲン(細胞の発生運命を決定する物質)やホルモンは濃縮された氣の一形態にすぎない。身体のコントロールには他の要因が存在する。体内の知的な制御システムはモルフォゲンを確かに使用しているが、私はそれと同じくらい電場(空間内の任意の点に働く電気的な力)を重要なものとして考えている。受胎の瞬間、陰と陽、精子と卵子が出会うとき、細胞の生命を本格的に始動させるものが電気である。この電気には知性がある。それは情報を伝達し、氣を持っていて、馬鹿ではない……電氣なのだ。
生命は電氣に始まり、生物の命ある限り持続する。電氣は、発達のあらゆる段階で、そして研究されているすべての生物で見つかっている。分化のまさに最初の段階――8つの細胞だけのとき――細胞たちは「緻密化」を行い、お互いの間に細胞間結合が形成されることがわかっている。細胞たちは、電気、知的な電気、つまり電氣で通信するために、これらの細胞間結合を使う。次に、細胞のボールは液体の内部コアを作りだす。この変化も電流(中心部方向へ動くナトリウムイオン)によって引き起こされる。
電流はものすごく小さく、電圧も1ミリあたりのミリボルト単位(mv/mm)ではあるが、研究されているすべての生物の発生において存在している。さらに電気は再生と治癒にも関わっている。この電気の流れを逆転させると、動物での胚の異常な発達および異常な再生を引き起こす。再び言うが、この電気は知性を持つ――電氣なのである。例えばクローン作製などで、我々が電氣を模倣しようとするならば、正しく行うために正確な電圧、特定の電流を使用しなければならない。心臓に電気ショックを与えるとき、コンセントから直接ワイヤーを胸と接続する医師はいない。正確な電流を使用し、場合によっては心臓のリズムに電気を同期させる。つまり、我々は電気に「知性」を加える。これは、まるでコンピュータの中を忙しく動き回っている電子が情報を運ぶ方法として同じである。これが生物学的情報を取り扱う電気――電氣である。
私たちの身体の電場は普遍的だが、それが成長へ与える影響に関する研究はまだ乏しい。西洋医学は、成長因子(微量で細胞の成長・増殖を促進する一群の物質)やモルフォゲンを分離することに血道を上げた。つまり、生物物理学ではなく生化学の方に。見ようとすれば、電氣は至る所で見出せるにもかかわらず、である。
中国人はその存在に気づいていた。なぜなら、電気的な生物としての感受性を高めて、訓練を積めば、我々はこの電氣を感じ、とらえることができるからである。経絡はそれぞれ異なっているように感じられ、ツボには異なる質感がある。このことは別に驚くべきことではない。経絡は異なる電気的特性を持っており、我々は「電気の身体」であることがわかっているからだ。修行を積んだ鍼灸師や武道家は、このエネルギーに敏感になる。彼らはこの違いを感じとって、利用しているのだ。
イギリスで最も尊敬された鍼灸師の一人、ラナルド・マクドナルドは、これに関してこう記している。彼が鍼灸の教授の下、中国で勉強していた頃、学友で懐疑的な医師の女性が教授にこう尋ねた。
「でも、氣って本当にあるんですか?」
教授は何も答えず、代わりにその女性の手を握って、合谷(L14)のツボを押圧した。すると、女性は痛みのあまり身体を折り曲げた。
そして、教授は「どうだい、氣はあるだろう?」と言ったのである。
教授は証明した。氣を用いなければ、圧覚点の生理学的説明はうまくできない。その証明は、他の何にもまして主観によるものである。親指と人差し指の間の水かき部分を押すと、どんなに屈強な男性でも無力になる理由を見つけてほしい。そして、その力を好きなように呼べばいい。
もし氣が生物学的な電気の形として現れたなら、電気のような挙動を示すと予想できるだろう。現代社会では、電気は毎日使われているので、私たちは電気について多くのことを知っている。電気自体は水と似たような形でふるまう。
鍼灸の古典では、しばしば氣と水が比較される。だから、非常の多くのツボの名前に「水」という漢字が使われていたり、手足の五兪穴が、井(井戸)、滎(わき水)、兪(小川)、経(川)、合(海)と呼ばれていたりする。もし、古典が水ではなく電気の現象に頼れたなら、古典は電気を用いただろう。電気の方が五兪穴を表すのによりしっくりするからだ。水は莫大な量を使って力を生む傾向があるが、身体の中を動く何かはほとんど見えない。いずれにしても、水は電気と似た形で動く。
●高圧な場所から低圧の場所へと移動する――電圧
●流れの中で動く――電流
●動くことで力を生む――ワット数
●流れる水のように、分離(絶縁)することもできるが、常に経路を探して、最も抵抗の少ない通路を通ろうとする――電気回路
●迂回できる――短絡
電気や水(もしくはモルフォゲン)を有するあらゆるシステムでは、高圧および低圧の領域が存在する。限られた空間に競合する物質が多いところでは高圧となる。つまり、低圧な場所では、物質が空間内を自由に遊走することができる。
身体の外側には基本的に電氣がないので、身体の内側は外部より高い電氣を持つことになる。電氣は、この勾配に沿って内側から外側へと移動する。そして、最も抵抗の少ない通路を流れる。ファッシア面はまさしくこの通路を提供する――これは内視鏡手術や、解剖の背景にある原理である。ファッシアの抵抗は非常に低いのだ。ファッシア面にある液体は、イオンが豊富で優れた電気伝導体であることがわかっている。血液を除けば他に類を見ない特徴として、この液体は、健康な状態では何ものにも妨げられずに動いていく。』P109
5.バイオフォトン
バイオフォトンとは「生物の生命活動に伴って自発的に放射する可視化が困難な微弱な自然発光」です。本書の中で、氣との関係性についてはわからない点は多いという認識をもって書かれていますが、興味深い事象なので気になった箇所をお伝えします。
『機械でしか測定できないくらいぼんやりではあるが、ヒトは光を発している。不思議なことに、小説の中で語られる「邪気」のように、それは爪から最も強く発してるように見える。この光はバイオフォトンと呼ばれ、科学的に認められた事実である。生きとし生けるものすべてがこの光を発している。 -中略- ドイツ人科学者フリッツ・アルバート・ポップは、バイオフォトンこそが氣の発現であると考えており、互いに支えあう細胞の力であると述べている。』P40
『氣との類似点はまさしくそこにある。氣の通路は身体の末端である手足の爪を通っており、そこのバイオフォトンの放出が最も強い。ヒトが病気になったり歳をとったりするとバイオフォトンの量が増えることがわかっているが、同じようなことが脳卒中の麻痺側でも生じる。鍼灸治療で、脳卒中患者のバイオフォトンのバランスが補正されていることがわかっている。
『バイオフォトンが氣であるかどうかわからない。しかし、明らかになっていることは、その多くがミトコンドリアから現れるということだ。ミトコンドリアは細胞の発電所であり身体のエネルギーの源である。一部の研究者はバイオフォトンがフリーラジカル損傷の指標であると考えているが、まだわかっていない。』
『バイオフォトンが干渉性であることを示す研究もいくつか存在する。干渉(コーヒーレンス)とは、エネルギーがどのようにエネルギー自体と連絡するか、光が光自体と同期するか、を説明する量子用語である。知性もしくは記憶を持った光は、量子物理学者だけが興味を持ちそうだが、身体の中でこんなことが起こっているなんてすごいことだ!ただ、このことに関する研究はまだまだ少ないので、暗闇から抜け出さないでいる。問題は、バイオフォトンの測定には、可視光の強度の千分の一の光を測定しなければならない。これには、とても高価な設備と、すさまじくたくさんの時間をじっと待つことを喜んで引き受けてくれる人が必要になる。』P41
『バイオフォトンは氣の物理的な表れかもしれない。もしくは、細胞性反応の副産物であるかもしれない。さらなる研究が必要であるが、それまでは、氣に関するどのエビデンスよりもバイオフォトンが最も興味を引くものである。バイオフォトンが示すものは、私たちの身体は電気のように光を作ることができ、この光が病気になると変化するということである。』P41
6.ツボ(経穴)
ツボ(経穴)については本書の内容と日本伝統医学研究センターで学んだこと、相澤良先生の師匠であった岡部素道先生のツボ(経穴)に対する考え方を比較したいと思います。
『経絡は氣の通路として存在している。鍼灸師ならば誰もが知っているこの経絡は、細胞内連絡として機能している。経絡上に存在するツボは、生理的にも病理的にもこの細胞内連絡が変化する場所である。優秀な鍼灸師であれば、この生理的変化がどこで起こるのか知っており、さらに重要なこととして、病気が生理的な反応を変化させることも知っている。したがって、病変の数が無限にあるように、ツボの数も無限にある。』P98
東邦医学 “硬結の経絡的研究”より
『経穴がどんな所にあるかを発見することが鍼灸治療家の最も至難な、しかも大切なことである。即ち経穴は、流、注、経、合、交会に外ならぬのであるが、原則として、硬結の発見を一つの手がかりとすべきであると想う。そして、それは経絡の変動と一致する。その経絡の変動を調節する事によって、疾病を治癒せしむるものである。換言すれば、疾病は、経絡の変動によって生ずるものである。経絡は一つの溝渠(給排水を目的として造られるみぞ)。この溝渠が内因外傷の客邪により、障碍が出来るのである。経絡を川に例えれば石その他の障碍物によって瀬が出来、流水の溜滞を来すとする。この瀬である障碍物が即ち硬結であり血氣の溜滞なのである。この硬結に治療を施し排除する事によって治癒効果があり、疾病が治るのである。』
医道の日本誌 “経絡治療座談会 病症論”より
『ツボとりは単に指先でちょっとさわるよりも、例えば、手の三里なら三里を取る場合に、手掌あるいは四指で軽く撫でてみる。そうして二、三回撫でてみますと、その中にある一点を見出す。その一点を今度はもっと強く押してみる。それが圧痛なり硬結が出てくる。これを一つのツボの本体として探り当てる。他と違った状態にツボは現れていると考えている。例えば、絡穴にしても、原穴にしても、よく触っていると、自分で触っても響くとか、あるいはキョロキョロのものが出てくる。あるいは陥下しているか、何か普通のところよりも違った感覚として指先に感じられるものがツボだと思う。その意味でツボは生きているとみている。ツボは経絡の変動とみている。』
両者を一つにまとめてみると、「ツボは生きている、硬結のような何か普通のところよりも違った感覚として指先に感じられるものがツボである。最も至難で大切なツボ取りは鍼灸師に委ねられており、経絡上に存在するツボは、生理的にも病理的にも経絡(細胞内連絡)が変化する場所である。さらに重要なこととして、病気が生理的な反応を変化させる。したがって、病変の数が無限にあるように、ツボの数は無限にある。そして、ツボ取りを委ねらえた鍼灸師はその経絡の変動(変化する経絡)を経絡上のツボを使って調節する事によって、疾病を治癒に導く」。という感じになると思います。
ここで、うまく整理することができなかった部分は、『病気が生理的な反応を変化させる(”閃く経絡”)』という表現と、『疾病は、経絡の変動によって生ずる(”硬結の経絡的研究“)』という表現です。もし、これを次のようにまとめることが許されるならば、両者に大きな差はないと言えると思います。
“健康”⇒“未病[東洋医学]”⇒“経絡の変動[東洋医学]”⇒“病”⇒“生理的な反応の変化[西洋医学]”
これは、「東洋医学の”経絡の変動”とは”病”の前段階の”未病”でみられるものであり、西洋医学の”生理的な反応の変化”とは”病”の段階で認識され、血液や尿などの臨床検査や各種画像検査の結果により確認された生理的な反応による変化」。という理解になります。
まとめと感想
冒頭でお伝えしたものが今回の学習の「まとめ」と言えます。それは次の一文でした。
「鍼治療とは、刺鍼ポイントのツボ(経穴)への刺激が、概念である氣の一部、「電氣」の知性に働きかけ、体表と内臓を結ぶ経路(経絡≒ファッシア)を通じて、乱れた状態を自然治癒力(ストレス適応を高め、栄養代謝を改善すること)によって元に戻す」。
また、以下は「感想」の類に入ると思います。
「生きていくために重い臓器を体内に抱えながら、しかも重力とも闘いながら動き回ることは大きな労力(エネルギー)を要するものです。この動くということによって、酷使されダメージを受けやすい領域は可動部、関節領域だと思います。
そして、負荷の集中によって普通とは違った状態を示すものをツボとするならば、その負荷とは動的および静的な筋・筋膜、腱・腱膜などの緊張状態(止まっている状態でも重力に抵抗し常に緊張している筋もあります[抗重力筋])と深い関係にあり、全身を覆ったボディスーツが各関節の動きによってできるシワやハリのように、面から線、そして線から点となって、ツボがつくられるのかも知れません。
ボディスーツのシワやハリは動きの特徴、強弱、繰り返し、持続時間およびそのヒトの体形などによって、さまざまな模様を見せると思いますが、その模様は無秩序に現れるのではなく、各関節や骨格などの構造的、機能的特性などにより代表的なパターンはある程度絞られるだろうと思います。また、物理的な作用は表面のボディスーツだけでなく、内部の臓器を包む膜などにも少なからず影響を与えるだろうと思います。あるいは炎症などの臓器に起こったダメージなどによって、それが内臓の膜にシワやハリをつくり、そして体表に変化をもたらすのかも知れません。
経絡の “経” とは縦、 “絡” とは横を意味しています。つまり、縦+横は面になります。経絡がボディスーツのシワやハリであるという意見は暴言に近いと思いますが、関係性があったら面白いと思います」。
ご参考:『人体の張力ネットワーク 膜・筋膜 最新知見と治療アプローチ』の目次のご紹介
第1部 科学的基盤
パート1 筋膜体の解剖
1.1 筋膜の一般解剖
1.2 体幹の筋膜
1.3 浅筋膜
1.4 肩と腕の深筋膜
1.5 下肢の深筋膜
1.6 胸腰筋膜
1.7 頸部と体幹腹側の深筋膜
1.8 内臓筋膜
1.9 頭蓋内における膜性構造と髄腔内の空間
1.10 横隔膜の構造
パート2 コミュニケーション器官としての筋膜
2.1 伝達器官としての筋膜
2.2 固有受容(固有感覚)
2.3 内受容
2.4 侵害受容:感覚器としての胸腰筋膜
2.5 全身伝達システムとしての筋膜
パート3 筋膜の力伝達
3.1 力伝達と筋力学
3.2 筋膜の力伝達
3.3 筋膜連鎖
3.4 アナトミー・トレインと力伝達
3.5 バイオテンセグリティ―
3.6 皮下および腱上膜組織の多微小空胞滑走システムの作用
パート4 筋膜組織の生理学
4.1 膜・筋膜の生理学
4.2 膜・筋膜は生きている
4.3 細胞外マトリックス
4.4 筋膜の特性に関するpHと他の代謝因子の影響
4.5 筋膜組織における流体力学
第2部 臨床応用
パート5 筋膜関連の障害
5.1 筋膜関連の障害:序論
5.2 デュピュイトラン病と他の線維収縮性疾患
5.3 “凍結肩(五十肩)”
5.4 痙性不全麻痺
5.5 糖尿病足
5.6 強皮症と関連症状
5.7 筋膜関連障害のトリガーポイント
5.8 筋膜関連の疾患:過可動性
5.9 足底筋膜の解剖学的構造
パート6 筋膜の弾性に関する診断方法
6.1 筋膜の弾性に関する診断方法
6.2 筋膜の触診
6.3 過可動性と過可動性症候群
パート7 筋膜指向性療法
7.1 包括基準と概要
7.2 トリガーポイント療法
7.3 ロルフィング構造的身体統合法
7.4 筋膜誘導アプローチ
7.5 オステオパシー徒手的治療法と筋膜
7.6 結合組織マニピュレーション
7.7 筋膜マニピュレーション
7.8 機能障害性瘢痕組織の管理
7.9 筋膜指向性療法としての鍼治療
7.10 刮痧(カッサ)
7.11 プロロセラピー(増殖療法)
7.12 ニューラルセラピー(神経療法)
7.13 動的筋膜リリース―徒手や道具を利用した振動療法
7.14 グラストンテクニック
7.15 筋膜歪曲モデル
7.16 特定周波数微弱電流
7.17 手術と瘢痕
7.18 筋膜の温熱効果
7.19 ニューロダイナミクス:神経因性疼痛に対する運動
7.20 ストレッチングと筋膜
7.21 ヨガ療法における筋膜
7.22 ピラティスと筋膜:“中で作用する(working in)”技法
7.23 筋骨格および関節疾患の炎症抑制を目的とした栄養モデル
7.24 筋膜の適応性
第3部 研究の方向性
パート8 筋膜研究:方法論的な挑戦と新しい方向性
8.1 筋膜:臨床的および基礎的な科学研究
8.2 画像診断
8.3 生体内での生体力学的組織運動分析のための先進的MRI技術
8.4 筋のサイズ適応における分子生物学的な筋膜の役割
8.5 数学的モデリング