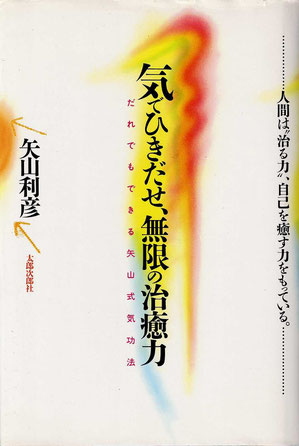本書の著者である矢山利彦先生は医師であり、佐賀県で“矢山クリニック”を開業されています。基本方針には「真の病因をつきとめ健康をクリエイトする」とあります。動画を拝見すると東洋医学と西洋医学に加え、歯科医科統合も実現されていることが分かります。
「健康を追求していくとどうしても口腔内衛生の健康を無視することはできない」という矢山先生のお考えに基づく方針ですが、口腔内衛生の問題は極めて重要だと思います。
※以前、ブログ“口腔内細菌との闘い”をアップしており、口腔内衛生については個人的にも興味を持っていました。

『Y.H.C.矢山クリニックのマークは、患者さん、ご家族や友人、医療従事者という3つの人のつながりと、西洋医学、東洋医学、その他の自然療法という3つの治療を融合して医療をおこなっていくことを意味しています。医師となって以来、数多くの患者さんと接し、治った方もおられますが、お亡くなりになり悲しく残念に思う方もたくさんおられます。そんな方々に、もっとこんなサポート・ケアをしてあげたかったと、ずっと考え続けてきたことをやっと形にできたのがこのクリニックです。』
矢山先生は、『西洋医学を学ぶことから医師としての歩みをはじめて、難病患者とのかかわりのなかで、“西洋医学の診断は精密化したが、根本的に治療できているのだろうか”という疑問につきあたって悩み、そして東洋医学の世界に分け入って、東洋医学の根本である気の勉強をかさねてきた。』とのお話をされています。
今回は医師(西洋医学)である先生が、東洋医学、気功、そして「気」をどう捉えているのかを勉強させて頂きたいと思います。
目次
まえがき
Ⅰ 気とであい、気をさぐる “治らない”病気への挑戦
西洋医学から東洋医学へ
●アメリカ方式で研修する病院で、外科医として出発する
●救急医療の現場で、人間の治癒力のすごさを知る
●難病患者をまえにして、治療のあり方に矛盾を感じる
●ムチウチ症の治療法を求めて、東洋医学とであう
●漢方薬と鍼治療から<気功>の世界へたどりつく
●武術の訓練のなかで、<気>への素地がつくられていた
●滝行は、無意識にかさねていた<気>の修行であった
●心身相関で病気が治ることを「心療内科」で学ぶ
<小周天法>を編みだすまで
●気功師・楊自正氏と出会い、はじめて<気>を体感する
●<小周天法>を求めて、中国の古典を読みあさる
●腹筋運動で熱を生じさせ、下丹田に<気>を集中する
●薬も鍼もきかない患者と<小周天法>の訓練をする
●感覚の敏感な手で、<気のボール>をつくる
●患者全員が<気のボール>を実感し、気を巡らす
天地の無尽の<気>との交流へ
●男女の<気>の流れの違いをO-リングテストで発見する
●磁気治療に着目し、小周天バンドを考案する
●外気治療による疲労と病状転移に悩まされる
●中国人のように早朝の樹木から「気」を取り込む
●天地の<気>と交流し、ものすごい快感・高揚感が訪れる
●人との出会いから、<大周天法>へのヒントをつかむ
●天地の<気>との交流法をヨーガのなかにさぐる
実践メニューⅠ
指気功
Ⅱ こころを診る、からだを癒す 臨床のなかの<気>
東洋医学診療部の創設へ
●患者自身の治癒力が働かなければ、病気は治らない
●症状はおなじでも、病気の深さはみなちがう
暮らしのなかからの歪みが生みだす病
●早食いが原因で腰痛になったケース
●クルマとハイヒールが腰痛をひきおこしたケース
●治らないムチウチ症で、病院がよいをつづけるケース
●家庭の不和がムチウチ症の再発をひき起こす
癌患者とその肉親の闘い
●癌を恐れる不安感が自然治癒力を萎えさせる
●末期癌の告知をめぐって、患者の夫と話しあう
●病状を告知して、癌に挑戦してほしいと訴える
●妻の末期癌を老夫婦はおだやかにうけ入れる
●病室へ足を運んでは、癌治療について話しこむ
●夫婦で気功をはじめて、病状は安定へ向かう
耕ちゃんの再生への歩み
●意識不明の息子に、母親は語りかけ歌いつづける
●一滴の水を飲みこむ力を回復させたいと願って
●イトコたちの声に反応して、はじめて耕ちゃんが笑った
●“ドーマン法”とであい、四年間の訓練をつづける
●車椅子の耕ちゃんの<気>の力の強さに驚かされる
●過労の限界にある母親に気功をすすめる
●母親の<気>の体験が、耕ちゃんの回復力を高めた
実践メニューⅡ
風風(ルンルン)気功
1.頭をゆるめる
2.丹田呼吸法
3.蝶形骨と後頭骨を整える
4.仙骨と尾骨をめざめさせる
5.寝て行う風風気功
6.二人で行う風風気功
Ⅲ 癒す力、生きる力の回復 <気>の可能性を求めて
西洋医学と東洋医学の統合をめざして
●特効薬と手術が、戦後医療の中心課題となる
●医療の対象は、臓器へ、病巣へと細分化していく
●栄養・漢方薬・気功でトータルに生命力を強める
●自然治癒力を高める東洋医学に、西洋医学を統合して
さまざまな領域で<気>の活用を
●21世紀にむけて、<気>をいかす可能性をさぐる
●<気>と脳波の関係で、心身ともに活性化する
●学校で<気育>ができれば、子どもは生気をとりもどす
実践メニューⅢ
小周天基本功
1.背骨を前後に揺する
2.背骨を左右に揺する
3.背骨をらせん状に揺する
4.頸をよこ8の字に揺する
あとがき
まえがき
『治療法がわかっていない病気になった患者さん、病状の進行した患者さんたちが、「この病気は治りませんという“宣告”をうけた」と話したり、「あとどのくらいの命でしょう」と言ったりするのを聞くと、私は悲しみといきどおりの気持ちが湧いてくる。そして、「よーし、何とかしてやるぞ」という負けん気の気持ちがムクムクと頭をもたげてくる。治らないということばをのみこみ、ギブ・アップすることを拒否して模索しつづけているあいだに、いつのまにか東洋医学に足をふみ入れ、さらに「気」の世界にたどりついた。』
Ⅰ 気とであい、気をさぐる “治らない”病気への挑戦
西洋医学から東洋医学へ
●漢方薬と鍼治療から<気功>の世界へたどりつく
・『漢方薬と鍼―はっきり効果が現れる方法を見いだして、私は夢中になり、研究と実践、治療をつみかさねていった。そのころ私は「鍼師・矢山」と呼ばれていたほどだった。一方、ムチウチがよくなったという話をきいて、これまで悩んでいた人たちが新しくやってこられ、いつしか、私のまわりはムチウチ症患者だらけになっていた。
そして・・・やはり、漢方と鍼で治療しても、どうしてもよくならない患者があらわれてきた。
さまざまな治療をうけめぐったがよくならない高齢の患者。ムチウチをきっかけにして仕事がうまくいかなくなった経営者.家事がさばけなくなったのを怠けとみられて、夫婦関係がこわれてしまった主婦。学校の成績がおちこんで悩む学生・・・そのほか、鍼も漢方も効かないという人は、みんなこころにつよい鬱屈を抱えているようだった。そういう人たちをみて、これは漢方でいう“気が虚している”ということではないか、という考えにたどりついた。
十五年まえのそのころ、東洋医学会でみたポスターの、「気の流れをよくする訓練としての気功」という文字に出会った。これは気功ゼミナールの開催の知らせだった。
“気功があの人たちに有効にはたらくかもしれない”という想いがひろがり、“よいのでは、と考えたら、なによりもまずやってみる”という、これも習性化している生き方が、私を<気>の宇宙にむかわせた。』
●心身相関で病気が治ることを「心療内科」で学ぶ
・大学で恩師・池見酉次郎先生と出会い、「心療内科」に触れたことが、気功へとつながる大きな基盤となった。池見先生は当時、日本ではまもない心療内科の初代の教授であり、気功、ヨーガなどにも造詣が深かった。
・池見先生の講義で、病気は身体だけの問題ではなく、こころと身体の両方、心身相関で治るということを教わった。さまざまな囚われや、こころの葛藤が消えていくとみごとに病気が治っていくということを学んだ。
・「自律訓練法」は気功にとって役にたった。例えば、皮膚の温度を自分の意識で変える訓練―自己暗示をかけるかたちで、ゆっくりとした呼吸とともに「手があたたかーい」とくり返す。訓練を続けることで手をあたたかくすることができるようになる。
※補足:百会(頭頂)→丹田(下腹部)→足へと血液が流れていくように意識(イメージ)するということは、まさに気が血を推動するという働きそのものに目を向けた行為だと思います。
・矢山先生がつくった気功の一つの柱は、「心身医学」といえる。非常に治りにくい胃潰瘍、原因不明の手足の麻痺、アレルギー疾患、これらはこころの軋轢で起きている場合がある。
<小周天法>を編みだすまで
●気功師 楊自正氏と出会い、はじめて<気>を体感する
・長い期間、病気が続いている人は病気を自分で治せるんだという気持ちが薄れてしまっていることが多い。どこかに治してくれる人がいるのではないかと思い、あちこちの病院を巡っている。
・漢方薬や鍼治療の効果があがらない患者さんは、必ずと言っていいくらい首や背中など身体のどこかに歪みがあった。
・医者から医療を受けるだけでは足りない。その人自身が、自分で自分を心身ともに持ち上げていけるようなプロセスとエクササイズが必要である。
・気功師 楊自正氏は脳外科医で武術の師から気功を学んできた。
・最初に学んだ気功が小周天だった。
・気が自由に出せるようになれば、さまざまな病気を治せるようになる。
・“意識、イメージの力によって身体の生理機能を自分で動かし、コントロールする”。
●<小周天法>を求めて、中国の古典を読みあさる
・小周天を簡単にまとめると―身体の真ん中の気の通路、前面が「任脈」、後面が「督脈」の、気の流れが盛んになると、全身の気の流れがよくなり、それで病気が治る―ということである。
・気を流すためには、まず、下腹部にある下丹田に気を集める。そのためには“下腹部に意識を集中し、息を吸うときも吐くときも下腹部を軽く緊張させ、そこに気が集まるとイメージし続ける訓練を行う。
●腹筋運動で熱を生じさせ、下丹田に<気>を集中する
・下丹田に気を集める方法として腹筋運動を取り入れた。
・『呼吸にあわせて、ゆっくり腹筋運動をしながら、意識を下丹田に集中する。つまり、腹部をふいごのように動かしながら、呼吸と熱のイメージと、筋肉の緊張と弛緩をくり返すわけだ。これを五十回から六十回もすると、下腹部に熱が発生する。当然なことで、運動による熱の発生だ。しかし、これをくり返していくうちに、だんだんすこしの運動回数で熱が発生するようになり、じょじょに運動をへらしていって、とうとう呼吸と腹筋の緊張だけで熱感を生みだすことができるようになった。』
●薬も鍼もきかない患者と<小周天法>の訓練をする
・漢方薬も鍼も効かない4人の患者さんに「気功訓練」を始めた。目的は小周天をマスターし自然治癒力を高め、病を克服してもらうことであったが、すぐさま壁にぶつかった。1番の問題は患者さんたちの背骨の歪みであった。身体の歪みは前後左右に屈伸したり、左右に捻じったりすることで身体の歪みがなくなる。これらは、ヨーガ、空手、太極拳から学んだものである。
・中国の導引にある、背骨を前後に波打つように動かす鳥と亀の型、左右に波うたせる龍の型を選んできた。そして、背骨をねじる動きに加え、これらの総合として、背骨を横8字に動かす熊の型を仕上げとした。

こちらは五禽戯という気功です。動画は「中国太極文化学院」さまから拝借しました。
・背骨の歪みをとる気功訓練が続いて、4人のうちの1人、女性の35年続いたという頭痛が少しずつとれていった。続いて長年の喘息で体力がなくなっていた朝山さん(仮名)も体力の回復に伴い、喘息の発作が減っていった。週1回の気功は新しい患者さんが加わり、症状の改善に至る患者さんが増えていった。しかしながら、患者さんたちが下丹田に気を集められるようにはならなかった。
・もともと、下丹田に気を集めるには、普通以上に健康で、体力・気力が充実していることが必要である。