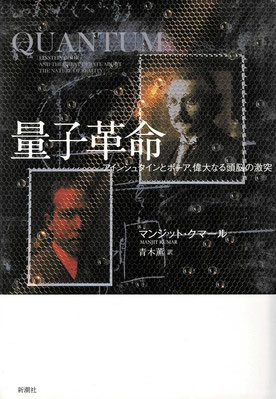19.古典物理学からの解放
●ボーアから教えられるかぎりのことを学んだハイゼンベルクは、多くの物理学者が踏み込めなかった量子的な概念は、慣れ親しんだ古典物理学の束縛から解放されることこそが、前進する鍵であることに気づきました。
『1924年9月17日にボーアの研究所に戻ったとき、22歳のハイゼンベルクは、量子物理学に関する単著または共著の優れた論文をすでに十篇以上も発表していた。彼は、自分にはまだ学ぶべきことがたくさんあり、それを教えてくれる人物としてボーア以上の適任者はいないことを知っていた。ハイゼンベルクは後年、「ゾンマーフェルトからは楽観的であることを学び、ゲッティンゲンでは数学を学び、ボーアからは物理学を学んだ」と述べた。ハイゼンベルクはそれからの七カ月間、量子論の困難を克服するためにボーアが採っていたアプローチをみっちりと教え込まれる。ゾンマーフェルトとボルンも同じ矛盾と困難に悩まされていたが、両者とも、ボーアほど四六時中その問題ばかり考えていたわけではなかった。それに対してボーアは、口から出るのは量子のことばかりというほど、この問題に没頭していたのである。
ボーアと徹底的に議論するなかでハイゼンベルクが思い知ったのは、「さまざまな実験結果を統一的に解釈することの難しさ」だった。たとえばコンプトン散乱もそのひとつだ。それは電子がエックス線を散乱させる現象で、アインシュタインの光量子仮説を支持する結果が得られていた。さらにド・ブロイが、波と粒子の二重性は、光だけでなく、あらゆる物質にまで拡張されると言い出したために、実験の解釈は何倍も難しくなったように思われた。教えられるかぎりのことをハイゼンベルクに教え込んだボーアは、この若い弟子に絶大な期待をかけた。「この苦境から脱出する道を見出すために必要なことはすべて、いまやハイゼンベルクの手中にあります」
1925年4月の末に、ハイゼンベルクはボーアの親切に感謝し、「これから先、ひとり寂しく研究を続けていかなければならないと思うと悲しいです」と言って、ゲッティンゲンに帰っていった。しかし彼は、ボーアとの議論、そしてその後も続いたパウリとの対話から、ひとつ非常に重要なことを学んだ―何か、とても基本的なものを捨てなければならないということだ。ハイゼンベルクは、水素原子の線スペクトルの強度という長年の未解決問題に取り組むうちに、何を捨てればよいのかがわかった気がした。ボーア=ゾンマーフェルトによる原子の量子論を使えば、水素の線スペクトルの振動数を説明することはできたが、その明るさ、つまりスペクトルの強度は説明できないと考えた。水素原子の原子核の周囲をめぐる電子の軌道は、観測することができない。そこでハイゼンベルクは、「原子核の周囲を軌道運動している電子」という、慣れ親しんだイメージを捨てることにした。それは大胆な一歩だったが、彼にはその道に踏み出す心の準備ができていた。ハイゼンベルクは以前から、観測できないものを絵に描いて示すというやり方が嫌いだったのだ。』
『ハイゼンベルクがこの新しい戦略を採るより一年以上も早く、パウリはすでに電子軌道という概念に疑問を突き付けていた。「一番重要な問いは、はっきりと規定された電子軌道について、どこまで語りうるのかということだと思います」と、彼は1924年2月にボーアへの手紙に書いた。この引用文の強調は、パウリ自身によるものである。彼はこのときすでに、排他原理へと続く道のりをだいぶ先まで進んでいたし、電子の殻が閉じるということの意味も考え抜いていた。そして同じ年の十二月にボーアに宛てた別の手紙のなかで、パウリは自分が提示した問題に、すでに次のような答えを与えていたのである。「原子をわれわれの偏見の鎖につなぐべきではありません。電子に普通の力学でいうような軌道があるという仮説も、そんな偏見のひとつだというのがわたしの考えです。量子的な概念を、慣れ親しんだ古典物理に合わせようとするのはやめなければならない。物理学者は自由にならなければならない、とパウリは言うのだ。最初にその妥協をやめたのが、ハイゼンベルクだった。彼はプラグマティックな観点から、科学は観測できることにもとづくべきだという実証主義の立場に立ち、観測可能な量だけを使って理論を作ることにしたのである。』
20.観測可能な量だけを使って作った理論
●ハイゼンベルクの花粉症は重症でした。その難敵である花粉のない島がヘルゴラント島です。ここでハイゼンベルクは誰もが待ち望んだ量子力学の扉を開けました。
『七十歳のハイゼンベルクは当時を回想して語った。その宿舎は、赤い砂岩が削られてできた、島の南端にある崖の近くにあった。三階の部屋のバルコニーからは、眼下に広がる村と海岸線を思い出しては、繰り返しそれについて考えた。ゲーテを読んでくつろいだり、小さなリゾート地で日課のように散歩や水泳をしたりするうちに、彼は内省的な気分になっていった。そうこうするうちに体調もだいぶ落ち着き、注意を散らすようなものがほとんどないなか、やがてハイゼンベルクの思索は原子物理学の問題へと戻っていく。ヘルゴラント島では、このところ彼に付きまとっていた暗い気分も消えていた。ゲッティンゲンから背負ってきた数学の重荷をあっさり投げ捨てると、彼はのびのびとした気分で、線スペクトルの強度の謎について考えはじめた。
ハイゼンベルクは、量子化された電子の世界を記述する新しい数学を探すにあたり、電子がエネルギー準位間を瞬間的にジャンプするときに生じる線スペクトルの、振動数と相対強度だけに焦点を合わせることにした。選択の余地はなかった。原子の内部で起こっていることについて教えてくれるデータは、そのふたつしかなかったのだ。量子飛躍という言葉が喚起するイメージとは裏腹に、電子がエネルギー準位間を遷移するときには、わんぱく坊主が塀の上から道路に飛び降りるときのように、空間を移動するわけではない。ある場所にいた電子が、次の瞬間、別の場所に現れるのだ―その中間のどこも通らずに、ハイゼンベルクは覚悟を決めて、観測可能な量と、それらに結びついたものすべては、電子がエネルギー準位間を遷移するときに行う量子飛躍という不思議な手品によって生じるのだと考えて納得することにした。かくして、電子が原子核のまわりを軌道運動しているという、太陽系のミニチュアのようなわかりやすい原子像は消滅した。
ヘルゴラント島という花粉のない天国で、ハイゼンベルクは、電子が行う可能性のあるすべての飛躍―状態から状態への遷移―を書き表すにはどうすればよいだろうかと考えた。エネルギー準位に関係して観測可能な量のそれぞれについて、ジャンプによって生じる変化を追跡するために彼が考えついた唯一の方法は、数を縦横に並べた表を使うことだった。』
『ニュートン力学で観測できる量にはさまざまあるが、ハイゼンベルクがその中で最初に考えたのは、電子の軌道だった。原子核からはるか遠くに離れたところで、一個の電子が軌道運動しているものとしよう―太陽系でいうなら、それは水星というより、むしろ冥王星に近い。ボーアが定常軌道という概念を持ち込んだのは、電子がエネルギーを放出しながら螺旋を描いて原子核に墜落するのを食い止めるためだった。しかしその電子の定常軌道が古典物理学で導かれたものと一致するためには、原子核からはるか遠くに離れたところで軌道運動している電子の軌道振動数(1秒間に軌道をめぐる回数)は、その電子が放出する放射の振動数に一致しなければならない。
これは突飛な思いつきではなく、対応原理―量子の領域と古典的な領域とのあいだにボーアが架けた概念的な橋―を巧みに応用した結果だった。ハイゼンベルクが想定した電子軌道はとても大きかったので、量子の世界と古典的な世界との境界線上にあった。ふたつの世界のあいだに引かれたその境界線上では、電子軌道の振動数は、電子が放出する放射の振動数に等しいはずなのだ。ハイゼンベルクは、原子内にあるそのような電子は、スペクトルのあらゆる振動数を生み出すことができる仮想的な振動子に似ていることを知っていた。マックス・プランクは四半世紀前に、それとよく似たアプローチを使ったのだった。しかし、プランクは恣意的な仮定を置き、正しいことがわかっていた式を力づくで導いたのに対し、ハイゼンベルクは、古典物理学の見慣れた風景につながるはずだという、ボーアの対応原理に導かれていた。いったん振動子を考えてしまえば、ハイゼンベルクは、その運動の特徴―運動量p、平衡の位置からの変異q、そして振動数―を計算することができた。振動数部vmnをもつ線スペクトルは、さまざまな振動子のうちの、どれかひとつによって放出されるはずだ。ハイゼンベルクは、量子的なものと古典的なものとが出会う、その中間地帯を詳しく調べて得られた結果は、原子の内部という未知の領域を探索するために利用できることを知っていたのだ。
ヘルゴラント島でのある夜遅く、突如として、ジグゾーパズルのピースが合いはじめた。観測可能な量だけを使って作った理論は、すべてのデータを再現してくれそうだった。しかしその理論では、エネルギー保存則は成り立つのだろうか? もしもエネルギー保存則を破っていれば、その理論はトランプの家のように崩れ落ちてしまう。自分の理論が、物理的にも数学的にも矛盾がないことを証明できるまであと一歩というところで、24歳の物理学者は、興奮と緊張のあまり、計算をチェックしながら単純なミスを繰り返すようになった。物理学の基本法則のひとつであるエネルギー保存則がたしかに成り立っていると彼がペンを置いたのは、夜中の三時ころだった。彼は点にも昇る心地だったが、動揺もしていた。後年、ハイゼンベルクはそのときのことを次のように語った。「はじめからわたしは、これは大変なことになったと思った。原子的な現象という上辺から、なんとも形容しがたい、美しい内部を覗き込んでいるような気がしたのだ。自然がこれほどまでに気前よくわたしの目の前に広げて見せてくれた、この豊かな数学的構造を、これから詳しく探っていかなければならないと思うと、めまいがするほどだった」。気持ちが高ぶってとても眠れそうになかったので、彼は夜明け前に、ヘルゴラント島の南端に向かって歩き出した。そこには海に突き出した岩があり、何日も前から登ってみたいと思っていたのだ。発見は興奮で吹き出したアドレナリンにエネルギーを注がれるようにして、彼は「たいした苦労もなくその岩によじ上り、太陽が昇ってくるのを待った」。』

画像出展:「MEISTERDRUCKE」
(The Grand Staircase, Helgoland, Germany, Photochrome Print, c.1900)

ボーアから全てを託されたハイゼンベルクが、ヘルゴラント島で発見したものは、量子力学の扉を開けた歴史的出来事だったように思います。
世界はひとつ、重力力学はふたつ。その答えは二つを見渡す境界線にあり、【波】(古典)と【粒】(量子)の構造はコインの裏表のように一体型とのことです。
生命の進化を淘汰とみれば、合理性や最適化が重要だと思います。重力力学が2つ存在するとすれば、そのような理由ではないでしょうか。
21.(A×B)-(B×A)≠ゼロ
●量子力学の扉を開けたハイゼンベルクが最初に著面した難題は、A×BとB×Aの答えが等しくないという奇妙な掛け算の謎を解くことでした。
『朝の冷たい光の中で、ハイゼンベルクのはじめの幸福感や楽観的な展望は色褪せていった。彼の見出した新しい物理学がうまく行くためには、X×YとY×Xが等しくないという、奇妙な掛け算を使うしかなさそうだった。普通の数なら、どの順番で掛け算をしても構わない。4×5の答えと5×4の答えは、どちらも20である。掛け算の結果は順番によらないというこの性質のことを、数学者は可換性と呼んでいる。数は、掛け算の交換法則を満たすので(つまり「可変」なので)、(4×5)-(5×4)はつねにゼロである。これはすべての子どもが学ぶ数学のルールだ。ハイゼンベルクを深く悩ませたのは、数の表の中のふたつの値を掛け算した結果は、掛け合わせる順番によって変わってしまうことだった。(A×B)-(B×A)は、必ずしもゼロではなかったのである。
彼の理論が必要としている、その奇妙な掛け算の意味がわからないまま、6月19日の金曜日、ハイゼンベルクはドイツ本土に戻ると、そのままハンブルクのヴォルフガング・パウリのもとに直行した。数時間後、誰よりも厳しい批判者であるパウリから励ましの言葉をもらったハイゼンベルクは、その発見をもう少し磨きあげて論文にするためにゲッティンゲンに向かった。二日後、その仕事はすぐにできると思っていたハイゼンベルクは、パウリに手紙を書き、「量子力学を作る仕事は遅々として進むみません」と伝えた。一日、また一日と時間が経ち、新しいアプローチを水素原子にうまく応用できないまま、ハイゼンベルクは追い詰められていった。
気がかりなことは山ほどあったが、ハイゼンベルクが確信していたことがひとつだけあった。何を計算するにせよ、「観測可能」な量のあいだの関係のみ、あるいは、現実には測定が難しいとしても、原理的には測定可能な量のあいだの関係しか使ってはならないということだ。彼は、自分の方程式に現れるすべての量が観測可能だということを公理として、「観測できない軌道という概念を完全に消し去り、その対応物で置き換える」ことに、「わずかばかりの努力のすべてを」注ぎ込んだ。
『その謎めいた掛け算規則には、どんな意味があるのだろうか? その問いがボルンに取り憑いて離れなくなり、彼はそれからの数日というもの、寝ても覚めてもそのことばかり考え続けた。ボルンはその計算規則に見覚えがあったのだが、それが何なのか思い出せなかったのだ。ボルンはアインシュタインに手紙を書き、この奇妙な掛け算がどこから出てくるのかはまだ説明できないけれども、「ハイゼンベルクの最新の論文がまもなく発表されることになるでしょう。まだよくわからないところもありますが、真実を捉えており、深いことは確かです」と伝えた。ボルンは自分の研究所にいる若手、とりわけハイゼンベルクを褒め、「彼の考えについて行くだけでも、わたしは相当努力が必要です」と書いた。くる日もくる日もその計算規則のことばかり考え続けたボルンの努力は、ついに報われた。ある朝、ボルンはふと、学生時代に受験したきり忘れていた、ある数学の講義のことを思い出した―ハイゼンベルクが出くわしたのは、行列演算だったのだ。行列演算では、X×Yは必ずしもY×Xにはならないのである。』
22.量子物理学の新時代の幕開けを告げる論文
●ハイゼンベルクに並ぶ天才とされたパウリは、ハイゼンベルクが書き上げた論文について、次のような言葉を送りました。「その論文は、かつてない希望と、新たな生きる喜びを与えてくれた。それで謎が解けたというわけではないにせよ、ここでまた、われわれは前進できるでしょう」と。
『六月の末、ハイゼンベルクは父親への手紙にこう書いた。「ぼくの仕事はと言えば、今のところ、あまりはかばかしくありません」。しかしそれから一週間ほどして、彼は量子物理学の新時代の幕開けを告げる論文を書き上げた。自分がやり遂げたことの意味にまだ確信がもてないハイゼンベルクは、写しを一部パウリに送り、申し訳なさそうに、二、三日のうちにその論文を読んで、返事をくれないかと頼んだ。ハイゼンベルクがそれほど急いでいたのは、7月28日にケンブリッジ大学で講演をする予定になっていたからだ。パウリはその論文を、「歓喜をもって」迎えた。パウリはある物理学者への手紙に、ハイゼンベルクの「その論文は、かつてない希望と、新たな生きる喜び」を与えてくれたと書いた。「それで謎が解けたというわけではないにせよ、ここでまた、われわれは前進できるでしょう」と、パウリは言い添えた。そして正しい方向に真っ先に踏み出したのは、マックス・ボルンだった。』
『ハイゼンベルクはその論文のまとめの部分に到達してからさえ、まだ逡巡していた。「ここに提案したような、観測可能な量のあいだの諸関係を使って量子力学のデータを求めるという方法は、原理的に満足の行くものと見なされるべきなのか、あるいはこの方法は結局のところ、現状ではきわめて込み入った問題であることが明白な、量子力学の理論を作るという物理的問題へのアプローチとしては不十分なものであるのかは、ここではごく表層的に採用したこの方法を、数学的により詳しく調べることによってのみ判定できるであろう」』
23.行列演算と量子力学
●ハイゼンベルクが発見した数の並びは、十九世紀の半ばにイギリス人の数学者アーサー・ケイリーが提唱した行列演算でした。この行列演算は数学では確立された分野でしたが、ハイゼンベルクの世代の理論物理学者にとっては未知の領域でした。また、このことに気づいたボルンはハイゼンベルクが作り出した枠組みを、原子物理学のあらゆる局面に適用できるような、論理的に矛盾のない枠組みに仕上げなければならないと思い、二十二歳のパスクアル・ヨルダンとともにこの大きな難問に取り組みました。
『ハイゼンベルクの掛け算規則は行列演算であることを突き止めたボルンは、位置qと運動量pを、プランク定数を含む式で結びつける方法をすぐさま発見した。その式はpq-qp=(ih/2π)Iと書くことができる。ここで、Iは、数学者が単位行列を使えば、それなしにはただの数にすぎない右辺を行列にすることができるのだ。この基本式にもとづき、それから数カ月のうちに、行列という数学の方法にもとづく量子力学が完成した。』
24.論理的に矛盾のない量子力学を定式化した「三者論文」
●猛烈な勢いで行列を勉強したハイゼンベルクは「三者論文」の作業に参加することができました。
『行列を知らないのはハイゼンベルクばかりではなかった。しかし彼は猛烈な勢いでその新しい数学を学びはじめ、まだコペンハーゲンにいるうちに、ボルンとヨルダンに追いつくほどの力をつけてしまった。十月半ばにゲッティンゲンに戻ったハイゼンベルクは、のちに「三者論文」として知られることになるその論文の最終バージョンを作る作業に参加することができた。彼とボルンとヨルダンの三人はその論文により、論理的に矛盾のない量子力学を定式化したのである。それはながらく探し求められていた、原子の新しい物理学だった。』
25.守備範囲の広い理論家
●シュレーディンガーの最初の論文は実験物理学だったそうです。先にご紹介した若き天才、パウリとハイゼンベルクは理論物理学に傾倒されており、この点が異なります。また、シュレーディンガーは放射性元素、統計物理学、一般相対性理論、色彩論[ゲーテによる光と色の研究]といった幅広い分野で四十篇以上の論文を発表しています。そして、一匹狼で、洒落ていて、気分屋で、親切で、寛大な、じつに愛すべき人間で、しかも、恐ろしく効率のよい、第一級の頭脳の持ち主だったとのことです。
『同僚の物理学者たちの見たシュレーディンガーは、放射性元素、統計物理学、一般相対性理論、色彩論といった幅広い分野で四十篇以上もの論文を発表している。堅実であるが、ずば抜けて優れているというほどもない仕事を重ねてきた、守備範囲の広い器用な理論家だった。シュレーディンガーの仕事のなかには、他人の研究を理解して分析し、分かりやすく説明する力量を示す総説がいくつもあり、いずれも高い評価を得てありがたがられていた。
11月23日、シュレーディンガーのコロキウム(談話会)には、当時二十一歳の学生だったフェリックス・ブロッホが出席していた。ブロッホがのちに語ったところでは、シュレーディンガーは、「ド・ブロイが波と粒子を結びつけた方法や、粒子の定常状態の軌道に整数個の波が収まるという条件を課すことで、なぜニールス・ボーアとゾンマーフェルトの量子化規則が得られるのかという条件を課すことで、なぜニールス・ボーアとゾンマーフェルトの量子化規則が得られのかということを、みごとにわかりやすく説明した」。しかし、波と粒子の二重性には実験の裏づけがなかったため(それが得られるのは1927年のことだ)、デバイは、ド・ブロイの議論は「子どもじみている」との感想を述べた。波の物理学には―音波、電磁波、ヴァイオリンの弦を伝わる波など、どんな波を扱うにせよ―その波を記述する方程式が必要だ。ところが、シュレーディンガーの説明した理論には、「波動方程式」がなかったのだ。ド・ブロイは、物質波の波動方程式を導こうとしたことはなかったし、彼の学位論文を読んだアインシュタインも同様だった。そのコロキウム(談話会)から五十年を経ても、ブロッホはそのときのことを鮮明に覚えており、デバイの指摘は、「あまりにも当たり前すぎて、みんなには軽く聞き流されたようだった」と述べた。
しかしシュレーディンガーは、デバイの言う通りだと思った。「波動方程式のない波では話にならない」のだ。そのとき彼はほとんど瞬時に、ド・ブロイの物質波に対する波動方程式を見つけてやろうと心に決めた。』
26.シュレーディンガーが「作った」波動方程式
●シュレーディンガーは親切で寛大だったとされていますが、駆け引きのない率直な性格で柔軟性、多様性も持っていたのではないでしょうか。デバイの酷評ともとれる「波動方程式のない波では話にならない」という発言を受け入れ、「量子の波動方程式をみつけてやろう」というポジティブな心が多くの物理学者に支持された直観的な方程式の発見を呼び込みました。
『クリスマス休暇から戻り、年明けに開かれた次にコロキウム(談話会)で、シュレーディンガーは声高らかにこう宣言することができた。「前回デバイが、波動方程式が必要だと言いましたが、さてさて、わたしはそれを見つけました!』。シュレーディンガーはその二週間のうちに、胎児のようなド・ブロイのアイデアを取り上げて、立派な量子力学理論に育て上げたのである。
シュレーディンガーには、どこから出発すればよいかも、何をすればよいかもわかっていた。ド・ブロイは、波と粒子の二重性というアイデアの妥当性の保証を、電子の定在波の波数が整数のときに軌道が閉じ、ボーアの原子モデルで許される電子軌道を再現できることに求めたのだった。しかしシュレーディンガーは、自分の探す方程式は、三次元の水素原子モデルを、三次元の定在波として再現できなければならないと考えた。水素原子は彼が見出すべき波動方程式の試金石になるはずだ。
波動方程式を探しはじめてまもなく、シュレーディンガーはまさに求める方程式を捕まえたと思った。しかし、水素原子に当てはめてみると、その方程式からは実験と合わない結果が出てきてしまった。その失敗の根本的な理由は、ド・ブロイが波と粒子の二重性というアイデアを得たときに、アインシュタインの特殊相対性理論と矛盾しないものを考え、そのよううなものとして提示していたことだった。ド・ブロイのやり方を手本にして進んでいたシュレーディンガーは、当然ながら、「相対論的」な形をした波動方程式を捜し、まさにそれを見つけたのである。そのころにはすでに、ウーレンベックとハウトスミットが電子のスピンを発見していたが、ふたりの論文が専門雑誌に掲載されたのは1925年11月下旬のことだった。当然ながら、シュレーディンガーが発見した相対論的な波動方程式にはスピンが含まれておらず、結果として、その波動方程式から出てきた結果は、実験とは合わなかったのだ。
クリスマス休暇が迫ってきたため、シュレーディンガーは相対性理論のことを気にするのはやめて、昔ながらの波動方程式を探すことに努力を集中した。相対論的でない波動方程式は、電子が光速に近い速度で運動するような場合には、相対論的効果が無視できなくなるため使えなくなる。
シュレーディンガーはそのことをよく知っていた。しかしとりあえずは、そんな波動方程式でも間に合ったのだ。』
『12月27日付のヴィルヘルム・ヴィーンへの手紙に、彼は次のように書いた。「目下、新しい原子理論と格闘しているところです。もっと数学を知ってさえいれば! ともあれ、それについてはわたしは非常に楽観的で、結果はとても美しいものになるだろうと予想しています。ただし、解くことができればの話ですが』
『シュレーディンガーはその波動方程式を「導いた」のではなかった―古典物理学から出発して、厳密な論理をたどるという方法では、その式は得られなかったのだ。そこで彼は、粒子に伴う物質波の波長と、その粒子の運動量とを結びつけるド・ブロイの式と、古典物理学のいくつかの式を睨み合わせて、その波動方程式を「作った」のである。簡単そうに聞こえるかもしれないが、シュレーディンガーがその式を書き下す最初の物理学者になれたのは、彼ほどの技量と経験があったればこそだった。シュレーディンガーはそれからの数カ月間で、その波動方程式を基礎として、波動力学という壮大な建物を作り上げることになる。しかしその前に、彼はそれがたしかに探し求めていた波動方程式であることを証明する必要があった。その方程式は、水素原子に応用した場合、水素のエネルギー準位に正しい値を与えてくれるのあろうか?
一月にチューリッヒに戻ったシュレーディンガーがじっさいに調べてみると、その波動方程式は、たしかにボーア=ゾンマーフェルトの水素原子のエネルギー準位を再現することがわかった。ド・ブロイは、電子の波として円軌道にぴったりはまる一次元の定在波を考えたが、シュレーディンガーの理論から得られるのは、もっと複雑な三次元の「軌道関数」だった。そして、波動方程式を解いて軌道関数が得られれば、その関数によって表される電子状態のエネルギーは自動的に決まる。ボーア・ゾンマーフェルトの原子の量子論では、正しいエネルギーの値を得るためには恣意的な条件を課さなければならなかったが、そういう操作はいっさい不要になったのだ。そればかりか、謎めいた量子飛躍さえもが、電子に許される三次元定在波から別の三次元定在波への連続的な遷移に取って代わられたかにみえた。1926年1月27日、「固有問題としての量子化」と題された論文が、「アナーレン・デア・フィジーク』に届いた。3月13日に同誌に掲載されたその論文には、シュレーディンガー版の量子力学と、水素電子に対する応用が示されていた。
シュレーディンガーは、五十年に及んだ物理学者としての経歴のなかで、年平均40ページ相当の論文を発表しづけた。とくに1926年には、256ページ相当という大量の論文を発表し、波動力学はさまざまな原子物理学の問題に幅広く利用できることを明らかにした。また、彼は、時間とともに変化する「系」を扱うことのできる、時間依存型の波動方程式を考え出した。時間とともに変化する系とは、たとえば、電子が放射を放出、吸収、散乱するような場合である。
2月20日、その最初の論文が印刷を待つばかりとなったとき、シュレーディンガーは自分の作った新しい理論に対して、はじめて波動力学という言葉を使った。』
27.ハイゼンベルクの難解な行列力学とシュレーディンガーの直感的な波動力学
●数学は苦にしないと思われる物理学者にとっても、当時、行列という数学はとても厄介な代物だったようです。そのため、難解とされたハイゼンベルクの量子力学(行列力学)に比べ、シュレーディンガーの量子力学(波動力学)は多くの物理学者を勇気づけました。この二つは同等のものとのことです。一つは行列、一つは微分方程式から生まれたということなのですが、私にはその同質性を理解することは到底できません。しかしながら、数学者にも劣ることのないハイゼンベルクと、最初の論文が実験物理学だったというシュレーディンガーの視点の違い、授かった才能の違いが二つの量子力学を世に送り出したのではないかと思います。
『冷たくて禁欲的な行列力学とは対照的に、彼が物理学者たちに与えたのは、使い慣れたおなじみの方法だった―彼の方法は、極度に抽象的なハイゼンベルクの方法よりも、ずっと十九世紀物理学に近い言葉で量子の世界を説明してあげようと、物理学者たちに語り掛けていた。謎めいた行列の代わりにシュレーディンガーが持ち込んだのは、物理学者の数学の道具箱にはかならず入っている微分方程式だった。ハイゼンベルクの行列力学は、量子飛躍と不連続性をもたらした。原子の内部を覗いてみたくとも、視覚的なイメージできるものは、そこには何もなかったのだ。シュレーディンガーは、これからはもう、「自分の直感を抑え込む必要はないし、遷移確率やエネルギー準位といった、抽象的な概念だけを相手にする必要もない」と述べた。物理学者たちがシュレーディンガーの波動力学を熱烈歓迎し、われ先にとそれを使いはじめたのは当然のことだった。
シュレーディンガーは、その論文の抜き刷りを受け取るとすぐに、彼が意見を聞きたいと思う物理学者たちにそれを送った。プランクは4月2日付の手紙に、「ずっと頭から離れなかった謎が解けたと言われて、真剣に話に聞き入る子どものように、あなたの論文を読みました」と書いた。それから二週間後にはアインシュタインから、「あなたの仕事のアイデアは、真の天才から沸き上がったものです」という手紙が届いた。シュレーディンガーは、「あなたとプランクが認めてくださったことは、わたしにとって世界の半分からの賞賛よりも大きな意味があります」と返信した。アインシュタインは、シュレーディンガーが決定的な前進を遂げたことを、「ハイゼンベルク=ボルンの方法は邪道であると確信するのと同じぐらいの強さで確信」したのだった。』
『このふたり以外の人たちが十分に理解するまでには、もう少し時間がかかった。ゾンマーフェルトは当初、波動力学は「完全なたわごと」だと思っていたが、やがて考えを変え、「行列力学が正しいことは疑う余地はありませんが、取り扱いが非常に難しく、おそろしく抽象的です。シュレーディンガーはわれわれを助けに駆け付けてくれました」と述べた。ほかにも多くの人たちが、ハイゼンベルクとゲッティンゲンの仲間たちの抽象的で奇妙な理論と格闘するよりは、波動力学の慣れ親しんだ方法を学び、じっさいに使いはじめてみて、ほっと胸をなでおろした。スピンで名をなした若手のヘオルヘ・ウーレンベックは、「シュレーディンガー方程式のおかげで助かりました。これでもう、不慣れな行列力学を勉強しなくてもすみます」と書いた。エーレンフェストやウーレンベックらライデンの物理学者たちは、行列力学を勉強する代わりに、数週間のあいだ毎日「何時間も黒板の前に立ち」、波動力学の驚くべき意味を汲み尽くそうとした。
パウリはゲッティンゲンの物理学者たちに近かったが、シュレーディンガーの仕事の重要性をすぐに見抜き、深く感銘を受けた。彼は行列力学を水素分子に当てはめて成功した際、ハイゼンベルクの方法のことは隅々まで調べ上げていた―彼がそれを迅速かつ徹底的に行ったことに、のちには誰もが驚くことになる。パウリがその論文を「ツァイトシュリフト・フュール・フィジーク」に送ったのは1月17日。シュレーディンガーが最初の論文を投稿するわずか十日前のことだった。パウリは、シュレーディンガーが波動力学を使って、行列力学を使った場合よりも楽に水素原子を扱っているのを見て愕然とした。彼はパスクアル・ヨルダンに次のように書いた。「その仕事は近年出た論文のなかで、もっとも重要な仕事のひとつだと思います。注意深く、集中してそれを読み込んでください」。六月にはボルンまでが、波動力学は「量子の法則を表す、もっとも深い形式」だと言うまでになった。
ハイゼンベルクは、ボルンが変節して波動力学の支持に回ったことを、「あまり良い気持ちはしない」とヨルダンに語った。彼は、シュレーディンガーが慣れ親しんだ数学を使っていることは、「信じられないほど興味深い」が、物理の内容に関するかぎり、原子レベルの出来事を正しく記述しているのは自分の行列力学のほうだと確信していた。』